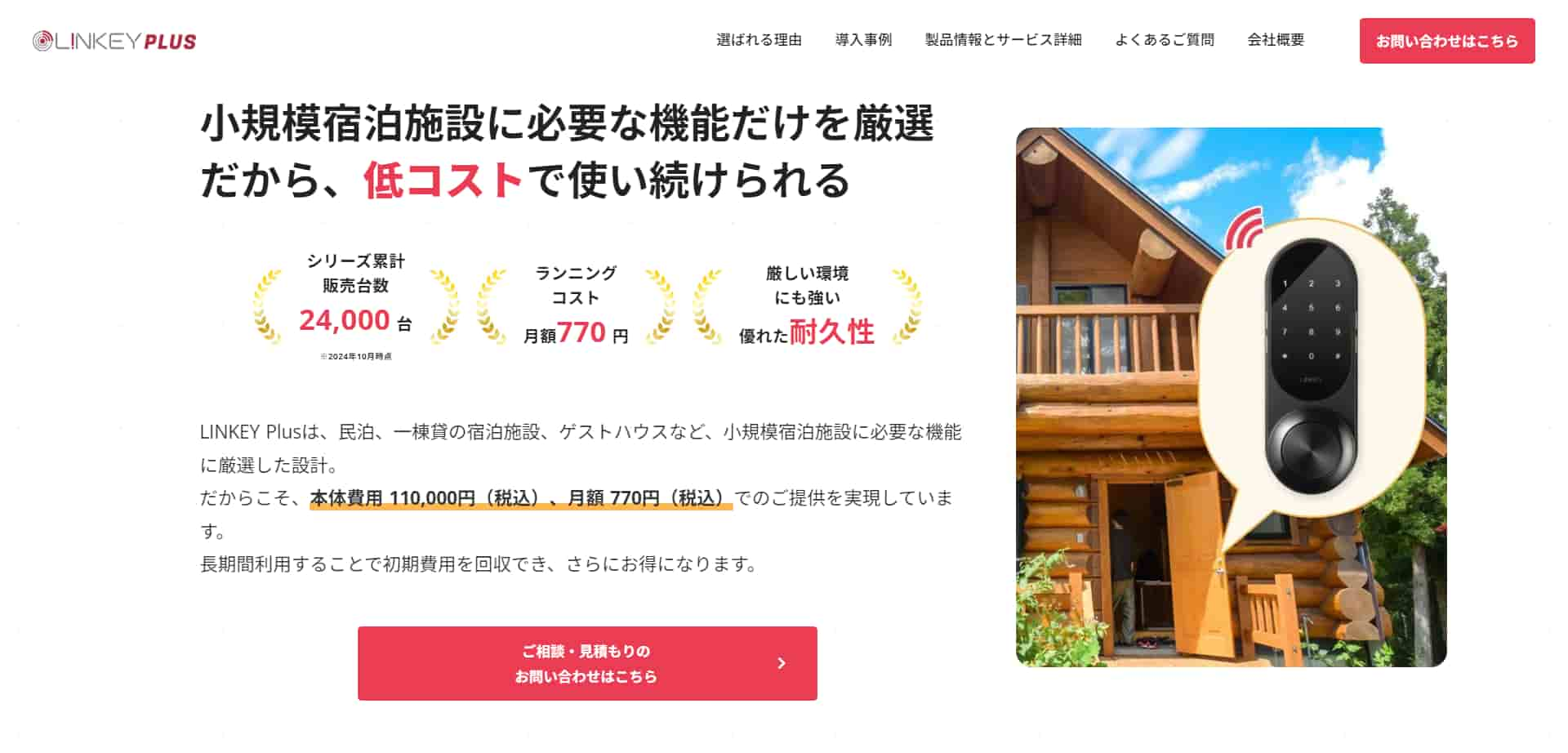スマートロックがハッキングされるリスク
スマートロックの利用を検討しているものの、ハッキングのリスクに不安を感じる方も少なくありません。ハッキングによって解錠に必要な情報が外部に漏れた場合、重大なトラブルにつながる可能性があります。ここでは、スマートロックのハッキングリスクと対策について解説します。
スマートロックにはハッキングされるリスクがあるか?
スマートロックは利便性の高い製品ですが、インターネットやBluetoothなどの通信機器を利用することから、ハッキングのリスクを完全になくすのは難しいです。最近の多くの製品ではセキュリティ対策が重視されており、ハッキングのリスクを低減する工夫がされています。
しかし、セキュリティ対策が不十分である場合はハッキングされるリスクが高まるので注意が必要です。これは、スマートロックに限ったことではありません。無線通信を利用している機器はハッキングのリスクがあります。
リスクの程度は、適切なセキュリティ対策が施されているかどうかに左右されます。Bluetoothによる解錠信号の送受信や、クラウド上で管理される情報にはリスクが伴います。これらに対して十分なハッキング対策を行っている製品を選べばリスクを抑えられます。
スマートロックの導入を検討している場合は、メーカー側が実施しているセキュリティ対策を確認したうえで検討しましょう。
スマートロックのハッキング対策
通信信号を更新する
スマートロックは、ドアの解錠や施錠に信号を用いています。この信号が常に同じである場合、情報が盗まれると不正に解錠される危険性が高まります。
一方、使用するたびに通信信号が新しいものに更新されるタイプを選んでおけば、仮に一度情報がハッキングされたとしてもその情報での解錠・解除はできません。同じ信号を再利用しない仕組みを採用したスマートロックを選ぶことが望ましいです。
強固な暗号化方式を用いる
そもそも、ハッキング行為があったとしても、情報を盗み取られなければ被害にはつながりません。そのためには、データを暗号化して送受信する仕組みを取り入れている製品を選ぶことが重要です。暗号化方式は製品ごとに異なるため、事前に仕様を確認することが重要です。
成り済まし防止対策
登録時に2段階認証を導入し、第三者による不正登録を防止する仕組みを採用した製品もあります。また、操作のたびにクラウド上でユーザー認証を行うシステムを搭載している製品は、登録後の不正使用防止にも効果があります。
なお、このサイトでは、導入する施設に合わせて、おすすめのスマートロックメーカーを厳選して紹介しています。併せて参考にしてください。
まとめ
できるだけ安全にスマートロックを利用するには、十分なセキュリティ対策が施された製品を選ぶことが重要です。個人でできる対策は限られているので、ハッキング対策の有無を確認し、それに応じた製品選びをしましょう。
仮に知らない間に自宅や会社事務所などで使用しているスマートロックがハッキングされ、不審者に侵入されていたとなると大変です。セキュリティ対策が不十分な場合、重大な被害につながる可能性もあるため、対策状況の確認が欠かせません。